今日は、親子について勉強してみたいと思います。
生物学的な親子関係と、民法上の親子関係は完全には一致しません。
血が繋がっていない子でも、親子とされる場合もあります。
では、詳しくみていきたいと思います。
1.親子の分類
民法の規定する親子関係には実親子関係(自然血族)と 養親子関係(法定血族)があります。
①実親子関係(血が繋がっている)
嫡出子(両親が正式に結婚している)・非嫡出子(両親が正式に結婚していない)
②養親子関係(血が繋がっていない)
普通養子(実親と縁が切れない)・特別養子(実親と縁が切れる)
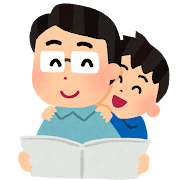
2.実子とは
血が繋がっている子供のことを「実子」と言います。
実子は、嫡出子と非嫡出子に分けられます。
その違いは、両親が結婚しているかどうかです。
①嫡出子
嫡出子とは婚姻関係にある男女を父母として生まれた子を指します。
嫡出子はさらに、①推定される嫡出子②推定の及ばない子③推定されない嫡出子に分けられます。
なぜこのように分けられるかというと、妻の産んだ子を「自分の子ではない」と主張したい夫が、どのような訴えを起こすべきなのかで決められています。
推定される嫡出子の場合は、夫の子であるという推定が働いています。
なので、これを覆すためには厳格な訴えをしなければなりません。
具体的に言うと「嫡出否認の訴え」を提起します。
推定の及ばない子や、推定されない嫡出子の場合は、夫の子であるという推定が働いていないので、もう少し緩やかな訴えでよいのです。
「親子関係不存在の訴え」を提起します。
①推定される嫡出子
民法772条
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
推定される嫡出子を、「自分の子ではない」と主張する場合、夫は「嫡出否認の訴え」を提起しなければなりません。
この、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければなりません。
この条文を見ると、私は数年前の大沢樹生さんのDNA親子関係裁判を思い出します。
実子であると思っていた息子が、実は血が繋がっていないのではないか?と、血縁関係を確定するために、大沢さんは「親子関係不存在の訴え」を提起しました。
大沢さんの長男の誕生日は、入籍よりちょうど200日・・・
つまり、あと1日でも長男が生まれるのが遅ければ、または、あと1日でも入籍が早ければ、長男は推定される嫡出子となっていたので、大沢さんは裁判を起こすことができなくなっていました。
(「嫡出否認の訴え」は、出生を知ってから一年以内に提起しなければならないからです。)
ちょうど200日で生まれたから、推定されない嫡出子として「親子関係不存在の訴え」を提起するに至ったのです。
なんか、運命のいたずらだなぁ・・・
としみじみ思いました。
では、嫡出子と嫡出否認の訴えについての条文を見てみます。
民法第774条
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
民法第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
民法第776条
夫は、この出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
民法第777条
嫡出否認の訴えは、夫がこの出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
民法第778条
夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫がこの出生を知ったときから起算する。
②推定の及ばない子
形式的には、772条の推定要件に合致していても、妻が、夫の子を懐胎することが事実上不可能であれば、夫の子であると推定を及ぼすことはできません。
ただし、推定の及ばない子も、戸籍上は嫡出子となっています。
たとえば、服役中に妻が出産したり、明らかに人種が違う子だったり、事実上の離婚状態が続いていた場合など、推定がおよびません。
推定の及ばない子を、自分の子でないと主張するときは「親子関係不存在の訴え」を提起します。
③推定されない嫡出子
推定されない嫡出子とは、婚姻前に懐胎し、婚姻成立後200日以内に生まれた子のことをいいます。
しかし、できちゃった結婚も多いため、判例は婚姻に先行して内縁関係がある場合には、婚姻成立後200日以内に生まれた子も嫡出子として扱うことにしました。(大連判昭15.1.23)
この場合も、自分の子でないと主張するときは「親子関係不存在の訴え」を提起します。
②非嫡出子
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女を父母として生まれた子を指します。
非嫡出子と母は、分娩の事実により当然に法律上の親子関係が成立します。

しかし、非嫡出子と父は、法律上の親子関係は当然には成立しない為、親子関係を成立させるためには、認知が必要となります。
民法第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
嫡出でない子は、認知によらずに父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することができない。なぜなら嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて成立するものであるからである。(最判平2.7.19)
3.認知の種類
非嫡出子と父との間に、親子関係を成立させるためには認知が必要となります。
「結婚はできないけど、子供は認知するよ」
ドラマやアニメで、割と見かけるシリアスな台詞です。
では、子供を認知するのとしないのとでは、何が変わるのでしょうか?
まずは、生まれてから以降の養育費を請求することができます。
更に、父親が死んだあとに、認知された子供は相続人となることができます。
認知することで、法律上の親子関係を成立させ、金銭的に責任をとります、ということになります。

認知には、任意認知と強制認知がありますが、次回はその認知の方法について詳しくみていきたいと思います^^
お付き合いいただきありがとうございました。
では、また~!!